工藤圭章編
高等専門学校教育方法改善プロジェクト
1994/03/24発行
こんな授業を待っていた
Ⅰ人文・社会・外国語系の授業がいまおもしろい
5. 解説最新情報
●世界の動き(214~226P)
今、「東欧」で何が起こっているか 田代文雄 沼津工業高等専門学校教授
89年の「東欧革命」は、56年のハンガリー事件や68年のチェコ事件が遠い記憶となって以33年間の時代的流れは、周縁に生じた激動の波を社会主義の中心にまで逆流させ、ソ連の解体を促し、戦後の東西対立構造に最終的ピリオドを打たしめるにいたった。以来、いわゆる東欧諸国はそれぞれの自由の道を歩き始め、「東欧」という地域概念も解体した。いうまでもなく、「東欧」とは社会主義政権を唯一の共通項とする、第二次大戦後の人工的な政治地理的概念であり、自然地理的区分でも、共通の歴史的文化圏を指すものでもないからである。
革命から四年、いま「東欧」でどんな事態が生じているのか。国の祝日からロシア革命記念日が消え、反革命とされてきた(ただし筆者が留学した20年前、すでに学者の多くが革命の文脈で論文を読めといっていた)ハンガリー事件勃発の日が革命記念日となり、戦前の国旗や王冠のついた紋章が復活した。問題は、政治・経済の急激な脱社会主義化による社会システムの作り替えで、旧部品と自前の未熟な新部品、西欧から輸入のハイテク部品とが齟齬をきたし、いびつな製品を生んでいることであるが、同時に従来ひとつにくくられてきた「東欧」が、本来もっていた多様・多相な姿をあらわにしつつある過程でもある。
市場経済への移行、私的所有権の承認(スターリン時代に没収された資産の返還措置)や国営企業の民営化などによる失業者、ホームレス、インフレ、貧富の格差、マスコミの低俗化(ポルノの氾濫)など資本主義の最も醜悪な面と、国営企業の役人経営者が民営化の名目で企業資金をもちだして私営の別会社を設立するといった旧体制の悪い面との結合などは前者の一例である。また、議会制民主主義は一党独裁制の反動として小党分立や民族主義的傾向、政治的アパシーなどを生み、ハンガリーではハプスブルクのオットー、アルバニアではレカ一世など第一次大戦期に亡命した旧国王継承者へのシンパシーも一部に現れた。また、知識人の復活も大きい。私が師事したブダペシュト大学のサバド教授が国会議長として来日したのには、会ってみて驚いたものである。作家・詩人で知られるチェコのハヴェル大統領、日本文学の翻訳もあるハンガリーのゲンツ大統領などもその一例である。
これらに対し、チェコとスロヴァキアの分離、ユーゴスラヴィアの解体とそれにともなうボスニア紛争、トランシルヴァニアのハンガリー系住民とルーマニア当局との軋轢、環境保護の立場からドナウ河ダム工事の中止を決定したハンガリーとその強行を図るスロヴァキアとの対立、あるいはEC準加盟を求めるハンガリー・チェコ・ポーランド先進三国および、それに続くスロヴェニア・クロアチアと、他の諸国との差異などは後者の例である。このような民族問題ともかかわる急激かつ複雑な差異の現れは、一般に分かりにくいようである。ことにボスニアで、「民族浄化」の名で行われている三民族相互の殺戮、集団レイプ、強制収容所といった悲惨な事態が、昨日までひとつの国の隣人として共生してきた人々の間になぜ起こったのか、連日報道される記事を追っても分からないというのが実状であろう。
この分かりにくさを考えてみると、三つのことに気づく。一つは「東欧」という言葉が1945ないし48年から89年までをさす歴史的用語となったにもかかわらず、自然地理的区分としての東ヨーロッパ(主にヨーロッパ・ロシアをさす)と紛らわしく、この地域の中世・近代にさかのぼる歴史的把握をしばしば阻害していること。ちなみに筆者がブダペシュトに留学した70年代に会ったハンガリー人の多くは、ここは東欧ではなく中欧であると称し、より正確にいう人は中欧東部という表現を用いていた。ハンガリーの 59年版大百科事典でも、東ヨーロッパとはほぼバルト三国以東、ウラル山脈以西のソ連のヨーロッパ部分をさすとあり、社会主義圏としての記述は全くない。なお、最新のアメリカの地理教科書では、ポーランド・チェコ・ハンガリー・スロヴェニア・クロアチアを中欧に、ブルガリア・セルビア・アルバニアなどを南欧に組み入れている。
第二は、「東欧」の多様・多相性が隠蔽されてきたこと。ことに宗教・民族問題は存在しないというのが社会主義政権の公的立場であった。また、それがあらわになったとしても、日本における関心の低さと社会主義幻想により無視されがちであった。例えば、トランシルヴァニアのハンガリー系住民に対する抑圧は、国内一般の人権抑圧とともに、筆者が20年前に実見した現実であり、ルーマニア人青年さえ激しいチャウシェスク批判をひそかに語ってくれた。その後、全欧安保会議で問題化したが、ルーマニア政府の強硬な否定と、対ソ自主外交路線の好イメージにかき消され、日本で関心を呼んだのはチャウシェスク政権崩壊の引き金となったティミショアラの虐殺事件に至ってである。
第三は、多数民族の「国民国家」と少数民族の「民族自決」との矛盾という、世界的な問題を含んでいること。この点に関しては後述する。
そこで、まず「東欧」解体の遠心力ともいうべき歴史的要因、すなわち本来もっていた多様・多相性をまず明確にしておきたい。これによって、ボスニア紛争の基本構造はかなりクリアーになる。「東欧」の多様性をマクロに整理すると、次のような模式図にまとめることができよう。一つは、「東欧」中央部を東西に走る非スラヴ系の民族的ベルトで、フィン=ウゴル語系のマジャール人(ハンガリー)とローマ人の後裔と称するロマンス語系のロマニア人(ルーマニア)からなり、その北側に西スラヴ人(ポーランド人・チェコ人・スロヴァキア人)が、南側に南スラヴ人(ブルガリア人・セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人など)が居住する。なお、スラヴ人の分化はかなり早いが、九世紀末のマジャール人の侵入・建国によって決定的に分断されたとされる。ちなみに、ユーゴスラヴィアは「南スラヴ人の国」の意である。
この横軸をなす民族的断層と垂直に交差する縦軸が、ポーランド東端から南のセルビア・クロアチア間を走る文化的断層線である。このラインの東側は東方教会(ギリシア正教)、西側はカトリックの文化圏である。セルビア語とクロアチア語は方言程度の差にすぎない同類の言語であるが、前者はキリル文字、後者はラテン文字を用いることにもこの断層がはっきりと見られる。このラインは四世紀の東西ローマの境界にほぼ相当し、東側はビザンツの滅亡後、オスマン=トルコの領域下に、西側はドイツ神聖ローマ帝国、その後ハプスブルグ帝国の勢力圏に属したところである。ユーゴスラヴィアはこの断層線の両側にまたがっている国で、問題のボスニアはちょうど断層線の真上に位置する。ついでながら、前述のEC準加盟に積極的な諸国が、いずれもこのラインの西側であることも注目される。遠い東西ローマの分裂は、A・トインビーがいうように、すべての歴史が現代史であることをまざまざと示している。
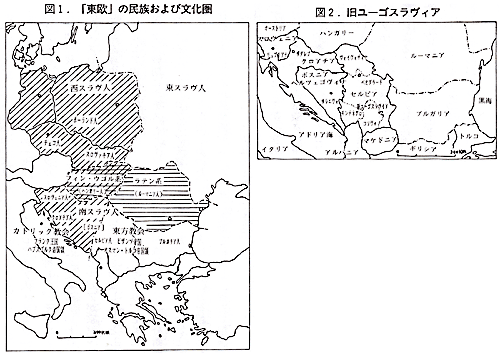
ユーゴスラヴィアは当初「セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人の王国」として第一次大 100万を超すともいわれる。このようななかで社会主義による民族横断的なパルチザン運動を組織し、独力で祖国を解放したのがクロアチア出身のチトーであったことは周知のとおりである。
チトーはパルチザン運動で培った社会主義と南スラヴィア人意識を紐帯として、民族問題は存在しないことを前提にセルビアを抑えつつ新たな連邦国家に組み替えた。その天才的バランス感覚で、コミンフォルムからの追放によるソ連の脅威を国内の結束にもちいると同時に、非同盟主義の指導者の一人として活躍、西側からの経済的援助(膨大な借款)をとりつけるという妙技を示した。60年代にユーゴスラヴィアに留学した友人の学者によれば、よくもこんなのんびりとした生産で少なくとも自分より裕福な生活ができるものかと目を疑ったという。これだけ裕福であれば、国内の不和は消えてしまう。しかし、チトーの晩期には返済の期限がおしよせ、第一次オイルショックで経済悪化がめだってくると、チトーの神話は、パルチザン体験の風化とともに崩れはじめた。
チトーの没後、隠されていた(凍結されていた)夫妻の性格不一致はふたたび頭をもたげ、そして「東欧革命」の波がこの国に決定的な二つのことをもたらした。第一は紐帯のひとつ、社会主義(共産主義者同盟)を吹きとばしたことである。第二は、東西対立構造があってはじめてもちえたこの国の国際的存在価値--だからこそチトーはそれをフルに活用した--を低下させ、西側の関心を奪いさったことである。もはや新たな借款はさして期待できなくなった。借金に追われれば、どんなに円満な家庭でも波風が立つのは当たり前で、まして性格不一致とくれば、経済先進国のスロヴェニア・クロアチアが足をひっぱられるのを嫌って別居=ゆるやかな国家連合を求めたのも不思議ではない(一人当たりのGNPはスロヴェニア約6300ドル、クロアチア約3600ドルに対し、マケドニア約1900ドル、セルビア2600ドル弱。93年推定)。しかし、あくまでも連邦に固執するセルビアはこれを拒否、不安定要因をきらうECも、東独との統一を果たして自信をふかめたドイツに引きずられてセルビアの説得を早々にあきらめ、離婚=分離独立を認めてしまった。ユーゴスラヴィアの解体である。その結果、ボスニアがどうなるかを知っていたのにもかかわらずにである。このへんに、第一次大戦前からのドイツの伝統的東方政策が見えかくれする。
先述したように文化的断層線上にあるボスニアは、連邦構成国中、唯一、民族名ではなく地域名40%,セルビア人(正教)32%、クロアチア人(カトリック)18%の民族構成をもつ。この地域は六~七世紀にスラヴ人が入って定着し、10世紀にはボスナと古名フム(のちのヘルツェゴヴィナ)の太守領を形成するが、セルビア、ビザンツ、ついでハンガリーの勢力下に入り、その独立運動はブルガリアから伝わった民衆的な異端の教派ボゴミールの運動と一体化、一時、ボスニア王国を樹立した。15世紀以降オスマン=トルコの領下となり、支配層は特権維持のためイスラム教に改宗、正教化した民衆を宗教的にも差別した。なお、スペインを追われたユダヤ人もかなり入ってきた。19世紀後半、トルコの衰勢にともない、オーストリア=ハンガリーが進出、列強の抗争の舞台となって、第一次大戦の発火点となったことは言うまでもない。
こうした歴史からも分かるように、一つにはムスリム人(トルコ人との混血もいるが、本来、南スラヴ人。ユーゴスラヴィアでは1971年より民族として公認)と正教徒との間に支配-被支配の関係があったこと、もう一つにはオーストリア=ハンガリーが進出に際しこうした宗教的・民族的対立を利用し煽ったことが、現在の混乱の遠因となっている。三民族の合意なしにドイツが分離独立をはやばやと認めたことに、かつての東方政策の影を見るおもいがしたというのは、このためである。これを追認したECは、少なくても和平の点で、ボタンを掛けちがったように思われる。
クロアチアが独立すれば、同国内のセルビア人(12%)がセルビアと切り離されて少数民族に転落するように、ボスニアでも逆に連邦にとどまれば、ムスリム人は圧倒的に不利になる。すなわち、多数民族と少数民族は国家の枠組みによって逆転する相対関係にあり、民族自決もまた少数民族が主張する以上、相対的なものである。ユーゴスラヴィアの場合、この国家の枠組みを当初、国家連合にするか、連邦ののままでいくかであった。一般に、このような民族の混住地域では、領土の一体性を守って多数民族が「国民国家」を主張し、国民化の名で少数民族の同化を図る例が多く、これに反発する少数民族の側も自らの「国民国家」をめざして激しい独立運動を展開する(1848年のハンガリー革命は、その最初の例。市民的自由を共通項に掲げて対オーストリア独立をはかり、封建国家から「国民国家」への転換を意図したが、国内少数民族は反発した)。それは同じものの表裏で、ボスニアの悲劇は現実を「国民国家」の理念に押し込もうとするところにあり、現実がそれを裏切っていることである。
確かに「東欧」諸国の多くは、長い大国支配のすえ第一次大戦後に独立を果たしたので、激しいナショナリズムが下位のナショナリズムを生み、国民的成熟ができていない、あるいは少数民族の人権を保護する民主的システムが未熟である。しかし、「国民国家」のモデルとされる成熟した西欧でさえ、いまもべルギーにおけるワロン人とフラマン人の対立激化、イギリスの北アイルランド問題などがあり、世界的に見れば民族問題(先住民族も含め)を抱えていない国家のほうがめずらしい。
ボスニアでは過去の長い歴史のなかで、幾度となく民族的・宗教的争いが繰り返されてきた。ボスニアのノーベル賞作家イヴォ・アンドリッチは、『ドリナの橋』でドリナ川の大洪水時に各地から集まって共同で対策をねるキリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒たちが--彼らはそれぞれ自分と同じ教徒の家にしか寝泊まりしないが--やがて国境が動くたびに対立を繰り返し、難民として村を捨てて移動する姿を、ボスニアの歴史のなかに描いている。ボスニアの人々は今よりひどい危機をのりこえて、彼らなりの民族の共生モデルをそのときどきに作ってきた。集まりが終われば、自分と同じ教徒の家に散って泊まるというのも、チトーのパルチザン組織で培った自主管理社会主義も共生モデルのひとつであった。社会主義が崩壊し、東西対立が終焉し、旧い国民国家の理念も破綻した現在、新しい共生モデルをつくりうるか、それをつきつけているのがボスニア紛争である。
結局、一般の民衆は戦火を逃れて村を捨て、アンドリッチが描いたように、それぞれの神に平和を祈り、和平が戻れば村に帰ってくるのである。難民の数は昨年でも一〇〇万を超す。確かに文化的断層線を埋めることは不可能である。「他信仰の隣人に対する文字どおり肉体的な嫌悪感や憎悪が、暴力や恐怖のすがたをとることもなく一世紀を過ぎることもしばしばあった。だがなにか大事件が起こり、確立していた規律や理性がゆすぶられ、法が数時間か数日のあいだ停止する時はいつも、暴徒の一部はついに恰好な理屈を見つけ、優雅で親切な社会生活と甘美な言葉で知られたこの町へなだれ込む。積年の憎悪と…破壊と暴力へのひそかな欲望が…火炎のように路上を占拠すると、唾をはき、噛みつき、打ち毀して、彼らより強大な勢力がこれを弾圧するか彼らの憤怒が燃え尽きるまで止むことがない」(アンドリッチ『サラエヴォの女』、田中一生訳)。しかし、燃え尽きれば「ふたたび何年も逼塞するのである」。
まさしく社会主義政権の崩壊という大事件で「確立していた規律や理性がゆすぶられ、法が停止する」と、各民族指導者は積年の憎悪と恐怖に駆りたてられたといえよう。彼らが求める民族自決は、和平になれば戻ってくる民衆のふるさととしての、多相だが一定の文化的・民族的生態系の破壊をもたらす(チャウシェスクが数百の農村共同体の再編によって、ハンガリー系住民を分散させ、その文化を破壊しようとしたのもその例である)。ボスニア紛争の解決は、EC・国連がいうような分割ではなく、おそらく多相だが一つの文化的・民族的生態系としての地域国家の視点をいれて、前ボスニア国連保護軍司令官モリヨン将軍がいうように(朝日新聞、93年11月3日)粘り強く当事者の合意をうるほかに道はないように思われる。